犬と猫、汗かくの??
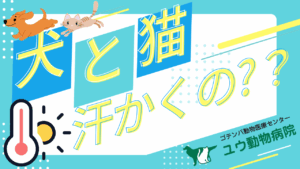
こんにちは!今日はワンちゃんネコちゃんの汗と体温調整のお話です。
人間は汗をかくことで体温を下げますが、「犬や猫ってどうしてるの?」と思ったことはありませんか? 実は、ワンちゃんやネコちゃんもわたしたちと同じように汗腺は持っています。しかし、その種類や体のどこにあるのかが人間とは大きく異なり、体温を下げるための方法は違います。
⭕️犬猫の汗腺ってどこにあるの?その役割は?
汗腺には、大きく分けてアポクリン腺とエクリン腺の2種類があります。
人間の場合、体温調節に重要な役割を果たすのはエクリン腺です。エクリン腺は全身にあり、ここから出るサラサラとした無臭の汗が蒸発する際に体の熱を奪い、体温を下げてくれます。一方、アポクリン腺はわきの下など体の一部に限られており、ここから出る汗はにおいがあり、フェロモン的な役割を持つと考えられています。
ワンちゃんネコちゃんの場合、汗腺の分布が人間とは逆になっています。彼らの全身に広く分布しているのはアポクリン腺です。アポクリン腺から分泌されるのは、体温調節のためではなく、その動物特有のにおいを持った分泌物です。これは動物同士のコミュニケーションの手段として使っています。散歩中にワンちゃんが地面のにおいを熱心にかぐのは、このような情報収集をしているからなんですね。
では、エクリン腺はどこにあるのでしょうか? 犬や猫のエクリン腺は、肉球と鼻の一部にしか存在していません。そのため、全身から汗をかいて熱を放出するという、人間のような効率的な体温調節はほとんどできません。これが、ワンちゃんネコちゃんが夏に弱いとされる理由の一つです。
⭕️犬と猫の放熱方法
ワンちゃんやネコちゃんは独自の工夫で体温を調節しています。
⭐️犬の体温調節はパンティング
ワンちゃんが暑さを感じたときによく見せる行動が、口を開けて舌を出し、ハァハァと速い呼吸を繰り返すパンティングです。これは、気道や舌の表面から水分を蒸発させることで、体の熱を奪う「気化熱冷却」というメカニズムを利用した放熱方法です。
しかし高温多湿な日本の夏では、空気中の湿度が高いため水分が蒸発しにくく、日本の夏にはあまり向いていない方法と言われています。さらに、パンティングは呼吸器に負担をかけるため、長時間続けると体力を消耗してしまいます。
⭐️猫の体温調節術は毛づくろいと「耳」
ネコちゃんは犬のようなパンティングをあまり見せません。主な体温調節方法は、独特な毛づくろいと、耳からの放熱です。
毛づくろいをする際、舌の表面にあるザラザラとした突起で被毛に唾液(水分)を移します。この唾液が被毛の表面で蒸発する際に、気化熱として体から熱を奪って体を冷やします。これも気化熱冷却の一つです。
また、猫の耳には多くの血管が通っています。体が熱いと感じると、猫は耳の血管を広げて、血液を耳の表面に多く流すことで、熱を効率的に外へ放出します。
しかし、猫は体調不良を隠すのが得意な動物です。熱中症になりかけていても、ギリギリまで気づかないことも少なくありません。そのため、飼い主さんがおかしいと思った時にはすでに熱中症が進行しているケースもあり、注意が必要です。
⚠️熱中症に特に注意すべき犬種・猫種
特に注意が必要な犬種や猫種はこちら。
- 短頭種(パグ、フレンチブルドッグ、シーズー、ボストンテリアなど):鼻が短く、気道が狭い。パンティングによる呼吸効率が悪い。熱をうまく逃がすことができず、非常に熱中症になりやすい傾向。
- 長毛種・大型犬(ゴールデンレトリバー、シベリアンハスキー、サモエドなど):被毛が長く量も多い。熱が体にこもりやすく、放熱しづらいのが特徴。
- シニア犬・肥満傾向の子:加齢により体内の代謝機能が低下し、体温調節能力が低下。肥満の子は体に脂肪が多く、熱をため込みやすい。
- 長毛猫・鼻ぺちゃ猫(ペルシャ、ヒマラヤン、エキゾチックショートヘアなど):長毛種は熱がこもりやすく、鼻が短い猫種は呼吸による放熱が不利になる傾向。
⭕️飼い主さん対策が命を守る鍵
このように、ワンちゃんネコちゃんは人間のように全身で汗をかくことができないため、暑さに弱い体の仕組みになっています。
だからこそ、飼い主さんの先を見越した対策が命と健康を守る上で必要不可欠! 夏の間は、エアコンで室温を快適に保つ、風通しの良い場所を提供する、新鮮で冷たい飲み水をいつでも飲めるようにしておく、散歩の時間を涼しい早朝や夜間に変更する、などの工夫がとても大切です。
もし、呼吸が速い・舌の色がいつもより赤いまたは青白い・ぐったりしている・落ち着きがなくうろうろする・よだれが多い・嘔吐や下痢などの異変に気づいたら、それは熱中症のサインかもしれません。一刻を争う事態ですので、すぐに動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。大切な家族のために、今年の夏も一緒に乗り切りましょう。

